9月7日(火)2年生総合
今日は2年生の「総合」のオンライン授業をzoom越しに見学しました。
2nen_sogo_9_7_1.mp4をダウンロード
(※毎度のことながら個人情報保護の観点からモザイク等のエフェクトを施し、解像度を低くしています。ご了承ください。)
最初に「なぞなぞ」を3つ楽しみ、朝のウォーミングアップ。その後、「宝物」についてブレイクアウトルームでグループごとに話し合いの時間を持ちました。話し合いの時に気をつけること、「こんな風に相手の話を聞けるとよいね。」とアドバイスがありました。
さて、今日のテーマは「ゆうびん」についてです。毎年、2年生は総合の時間に、郵便について学んでいます。今日は各自家にある葉書を手に、「葉書を見て気づいたこと」を考え、先程のグループで発表しあいました。ブレイクアウトルームをのぞいてみると、担任からアドバイスされたことを生かして、相手のこを考えながら聞き、それに対して自分の考えや質問をしていました。学年を追って段々と人とのコミュニケーションを取ることが上手になっていってほしいと願っています。
次回は、それぞれのお爺さまやおばあさまに宛てて、手紙を書くそうです。遠くに離れて住んでいらっしゃるお爺さまやおばあさまがいらしたら、このコロナ禍ではより一層喜んでいただけることでしょう。
心を込めて書いてください。
9月6日(月)4年生算数
先週から始まった2学期、今日はzoom越しに4年生の算数の授業を見学しました。
今日の授業は「がい数」でした。パワーポイントのスライドを工夫して、スライドに提示されている数についてクイズ形式で考えていきました。途中、2500という数字をどのように考えるか意見を出し合い、理解を深めました。チャットルーム機能を話し合いや答え合わせにも使っており、みんな集中して学習に取り組んでいました。学校での授業と同じように、自分の意見や考えを積極的に発言していて元気いっぱい。この後の「総合」の時間でも活発に活動できたのではないかと思います。
4nen_meth_9_6.mp4をダウンロード
※毎回のことですが、個人情報保護のため、画面全体にモザイク等のエフェクトを施しています。見づらい点がありますことをご了承ください。
9月3日(金)6年生授業
オンラインでの学校が始まって3日目、今日は6年生の国語の授業をzoomごしに見学しました。
まず出欠と連絡事項が伝えられ、そして国語の授業に入りました。最初に漢字の説明があり、次に問題集に載っている四字熟語についての学習が始まりました。zoomのブレイクアウトルーム機能を使って2人組に分かれ、多くの四字熟語の中から選んで、その四字熟語がわかるように演じる、という課題です。ひと組のルームに実際に入って見学したところ、とても集中して楽しそうに話し合っていました。7分のブレイクアウトルームでの話し合いの後、いくつかのペアに、全員がいるところで演じてもらいました。ユーモアのある演技にびっくり!たった7分で話し合い、生き生きと表現できるなんてすごいなあ!と思いました。普段の学校生活の中でも、プレゼンをしたり、話し合ったりする機会を大切にしていたのだろうな、と感じました。
6nen_9_3koku.mp4をダウンロード
今年の6年生は最高学年ですから、当然ながらICTをかなり使いこなしている子どもたちです。
ビデオ機能のオンオフ、だけでなく、ビデオ参加していない場合に画面から自分を消す方法なども上手にできていました。(画面で発表の子どもたち二人だけになっていましたね。)もちろん学校で実際に机を並べながらの授業が一番ですが、休校時、zoomならではの活動も、貴重な経験となるに違いありません。
明日は授業は土曜日なのでお休みです。
また来週、どこかの学年の授業をお伝えしたいと思います。(どこにしようかなー?)
9月2日(木)1年生授業
昨日の始業式を終え、各クラス時間割に沿ったオンライン授業が始まりました。
教員が持っているiPadには、メッセージ通知の着信がひっきりなしにあります。各クラスの授業が確実に進行し、子どもたちがロイロノート・スクールやGoogle classroomを使ってオンラインでの学習を進めている様子がわかります。
 今日は、1年生の国語の授業の様子をzoomごしに見学しました。
今日は、1年生の国語の授業の様子をzoomごしに見学しました。
2nen_9_2_koku.mp4をダウンロード
※個人情報保護のため、解像度を落とし、画面全体にぼかしのエフェクトを施してあります。見辛いと思いますがご理解ください。
1年生はオンライン授業は初めてなので、昨日に続いてzoomの機能の使い方やマナー、Google classroomへのコメントの書き方を学ぶところからスタートしました。自分が話す直前にミュートを解除する練習として、出席をとりました。担任が名前を呼ぶと、一人ひとりタイミングよくミュートを解除して、元気な返事をすることができていました。続いて国語の学習ではカタカナを学びました。最後は、ビデオ機能をオフにして休み時間となりました。zoomの使い方に慣れてくると、グループでお話しすることもできるようになります。学校とはまた異なる学びの形を経験することも大切なことかもしれません。
オンラインで新学期が始まりました。
9月1日(水)、2学期が始まりました。2学期は当面の間、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、zoomを使ってオンラインで一部の授業を行い、専科など実技系の授業は主に動画の配信での学習となります。夏休み中は静かだったGoogle classroomのコメント欄が、昨日から、担任や専科からの連絡や子どもたちからの返信で賑やかです。いよいよ新学期が始まった感じがします。
始業式に際しての校長先生のお話は事前に収録されました。各クラスのGoogle classroomに事前に配信されています。zoomで行われた各クラス単位の始業式の中で画面共有をして視聴したクラスもあれば、事前に子どもたちがそれぞれ視聴したクラスもありました。
今日は、5年生のクラスの様子を動画でお伝えします。個人情報保護のため、画面全体にエフェクトをかけていますことをご了承ください。雰囲気だけでもお伝えできればと思います。
5nen_9_1.mp4をダウンロード
5年生は、今後学年でzoomを使ってのイベントを行いたいということで、始業式の後、有志の子どもたちは時間をおいて再びオンライン上で話し合いを行っていました。20数人の子どもたちが企画委員として協力したいということで、集まった子どもたちは6人ほどのグループに分かれて、ブレイクアウトルーム機能を使って、グループディスカッションを行っていました。楽しそうに意見を交換していました。
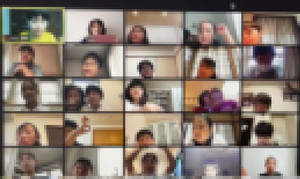
 6年生のクラスは、まず画面共有で校長先生の話を全員で見て、その後校歌を歌いました。zoomだとどうしても時間差ができてしまいますが、そこはご愛嬌。今まで何度も歌っている校歌をzoomで歌うということも貴重な経験となったことでしょう。
6年生のクラスは、まず画面共有で校長先生の話を全員で見て、その後校歌を歌いました。zoomだとどうしても時間差ができてしまいますが、そこはご愛嬌。今まで何度も歌っている校歌をzoomで歌うということも貴重な経験となったことでしょう。
 1年生は、オンライン授業は初めてです。最後のところだけしか映像がありませんが、「さようなら、またねー!」という言葉に、オンラインで会えたことの喜びが伝わってきました。
1年生は、オンライン授業は初めてです。最後のところだけしか映像がありませんが、「さようなら、またねー!」という言葉に、オンラインで会えたことの喜びが伝わってきました。
1nen_9_1.mp4をダウンロード
明日からいよいよ授業が始まります。各クラスの様子を映像や写真でお伝えしてまいります。
※動画や画像には、個人情報保護のためエフェクトをかけています。見づらいかと思いますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
秋が少しやってきました。もうすぐ2学期です。
8月もあとわずか。学校の通学路には、ちょっと気の早い、可愛らしいどんぐりが転がっていました。
まだまだ暑くて、秋なんていつ来るのかな?という感じですが、自然の時計はゆっくりと動いているのですね。


9月1日から2学期が始まります。でも、新型コロナウィルスの感染悪大防止のため、学校にみんなで集まることはできません。早速オンライン授業が始まりますが、先生たちも楽しく、充実したオンライン授業をしたいと準備しています。画面越しですが、森村っ子の皆さんに、久しぶりに会えるのが楽しみです。
FESTIVAL OF CODING 2021レポート【その2】
先日、この「今日の森村っ子」でご紹介した、FESTIVAL OF CODING 2021の様子の続報です。「教育ICTリサーチ」に8月9日に公開されましたので、以下にリンクを貼っておきます。掲載されました。
教育ICTリサーチの紹介ページ
1学期に学校の個別授業公開に参加された方や、以前学校を見学された方の中で気づかれた方もいらっしゃるかと思いますが、メディアルームに7月終業式前後に大型のスクリーン2台が設置されました。
新学期からはより充実した設備の中で、ICTの授業が展開されます。今から楽しみですね!
JAXA人工衛星ペーパークラフト
「今日の森村っ子」をご覧の皆様の中にも、夏の休暇を過ごしている方がいらっしゃることでしょう。
1学期、6年生の理科の授業で扱った、「月と太陽」の単元では、JAXAの人工衛星のペーパークラフトに取り組みました。
理科室前の廊下天井を見上げると、6年生の児童が作ったクラフトが展示されています。
写真は、「きずな」(WINDS)と「だいち2号」(ALOS-2)。


「きずな」は人工衛星超高速インターネット衛星で、アジア・太平洋地域のデジタルデバイド解消とギガビット級のインターネット通信技術の確立を目的に開発された衛星です。2011年6月に実証実験を終えましたが、2011年3月11日に発生した東日本大震災の際には、地上の通信設備が甚大な被害を受ける中、「きずな」によってブロードバンド通信環境を構築して、被災地からでもインターネットが利用できるようにするなど大活躍しました。
「だいち2号」はその名の通り、衛星から地上までの距離の変化を数cmの精度で検出できる性能を持ち、地震・火山活動などの観測に役立っています。
JAXAのホームページに他の人工衛星の型紙も掲載されているので、この夏、ダウンロードして、涼しい部屋の中での工作にいかがでしょうか。写真は6年生児童、理科教員の製作した作品。これより上手に作れるかな?挑戦してみてくださいね。
パナソニック・フジテレビ・関テレと子ども向けワークショップ
8月5日、6日にパナソニックの映像制作の教育プログラムKWNの一環で、オンラインでのワークショップが開かれました。その様子が、産経新聞のインターネット版に掲載されました。
今年度も5年生有志の子どもたちがKWNの映像制作プログラムに取り組んでいます。1学期もメディアルームでミーティングを重ねていました。どんなテーマに関心を持ち、深め、伝えていこうとしているのか、今からとても楽しみです。
記事はこちら
FESTIVAL OF CODING 2021が行われました【その1】
7月の学習会で行われたFESTIVAL OF CODING 2021の様子が「教育ICTリサーチ」に掲載されました。このワークショップは、6年生希望者が対象です。希望者のうち抽選で選ばれた6名の児童が、本校メディアルームでコーディングに取り組みました。じっくり時間をかけ、試行錯誤を繰り返しながら様々なミッションにチャレンジしました。その様子について写真と文章で綴られていますので、どうぞご覧ください。
教育ICTリサーチの紹介ページ

 今日は、1年生の国語の授業の様子をzoomごしに見学しました。
今日は、1年生の国語の授業の様子をzoomごしに見学しました。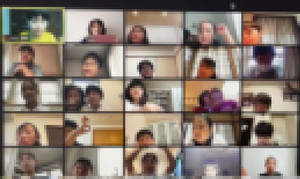
 6年生のクラスは、まず画面共有で校長先生の話を全員で見て、その後校歌を歌いました。zoomだとどうしても時間差ができてしまいますが、そこはご愛嬌。今まで何度も歌っている校歌をzoomで歌うということも貴重な経験となったことでしょう。
6年生のクラスは、まず画面共有で校長先生の話を全員で見て、その後校歌を歌いました。zoomだとどうしても時間差ができてしまいますが、そこはご愛嬌。今まで何度も歌っている校歌をzoomで歌うということも貴重な経験となったことでしょう。 1年生は、オンライン授業は初めてです。最後のところだけしか映像がありませんが、「さようなら、またねー!」という言葉に、オンラインで会えたことの喜びが伝わってきました。
1年生は、オンライン授業は初めてです。最後のところだけしか映像がありませんが、「さようなら、またねー!」という言葉に、オンラインで会えたことの喜びが伝わってきました。


